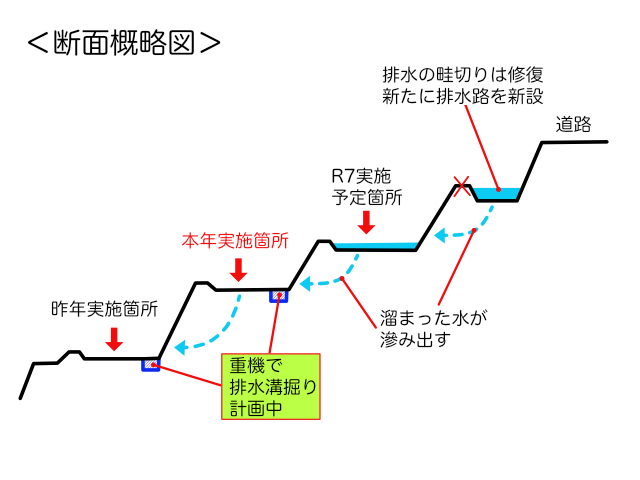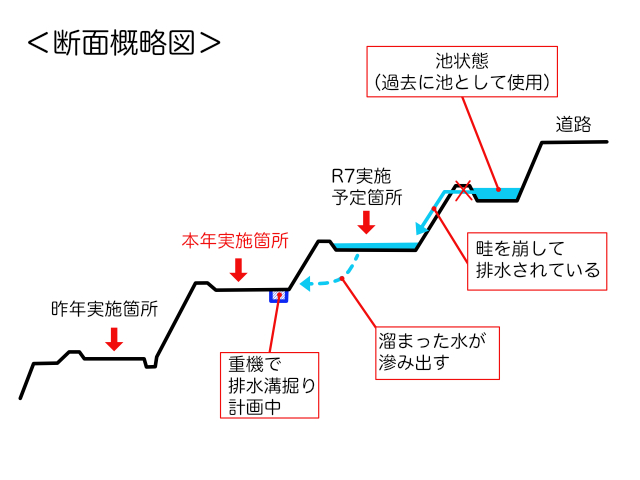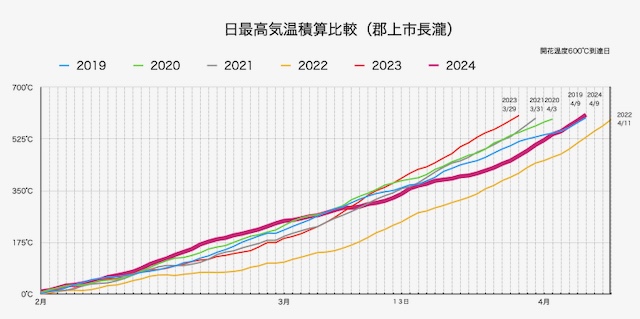毎月第1日曜日は「栃洞景観づくりの日」。
2021年に「郡上市景観百景」にここ「栃洞地区」が認定されてから、地区の「景観づくり」を行なってます。
今年は「景観整備の日」の天候不順が続いていて、昨晩もそこそこ雨が降ってましたので『大丈夫か?』と心配していましたが、お陰様で朝から良い天気になり無事に今月の「景観整備の日」を行えました。
本日実施するのは、
1:栃洞地区の草刈り(男性陣)
2:夏に向けての植栽の準備(女性陣)
この日は「ぎふ・ロードプレーヤー」の日でもありましたので、男性陣は「道沿いの草刈り」を特に重点的に行いました。
それでは当日の様子を紹介してみましょう。

朝8時の集合時間ですが、みなさん、早めに集まってくださってます。
というのは、この時期は『遅く始めると暑さで大変』なので、その辺りを思っての暗黙の了解です。(笑)
『誰が何を行うか』を簡単に打ち合わせ、それぞれが分担の場所に向かいます。
私の担当は他の方と2人で、集会所までの道沿いを行います。

この擁壁の上の部分と、

この擁壁の上を行いました。
『え?これで刈ってあるの?』と思われるかもしれませんが、この時期にはスズメバチが薮の中に巣を作っている可能性が高いので、この程度で止めました。

3名の方には、先月行った中洲の続きを刈っていただきました。
今回は写真の木の生えている場所、中洲の半分くらいの面積です。
この場所は写真では分かりませんが、地面が平坦で無くなかなか苦労しますが、この様に綺麗に刈ってくださいました。
そして、残りの方々に集会所から浄水場までの間を担当していただき、それぞれ他の担当箇所が終わったら合流する事にしていました。

ガードレールが有る場所は、それが邪魔で刈りにくいのですが、綺麗に刈っていただいてます。

ここも気持ち的にはもっと奥まで綺麗にしたいのですが、私が担当した所と同じで奥への刈り込みは蜂の巣の危険が有るので、安全第一で、これぐらいで良しとします。

やっと刈ってる様子の写真を載せられます。
私自身も作業を行なっていますので、なかなか写真を撮りに回れないのです。
草刈りの作業ではお互いの草刈機が干渉して危険が無い様に、、こんな感じに間合いを取って刈っていきます。
と言うのは、草に隠れている木の株や倒木に草刈機の刃が触れると「キックバック」と言って、予想外の方向に草刈機が跳ね返されたりするのです。
そんな際に、近くにいると大変な事になりますからね。
さて、男性陣が草刈りを行なっている間、女性陣はと言いますと、

春に設置した植栽の手入れと、

前回の「景観整備の日」に蒔いた朝顔が芽を出したので、「グリーンカーテン」の場所にプランターを移動させてます。

プランターを移動させたら、男性陣の背の高い方にネットを設置してもらってます。
昨年は暑過ぎたのか、種を蒔いた時期が悪かったのか、思ったほど「グリーンカーテン」にならなかったので、今年は良い具合になると良いなと期待してます。

他にも、夏に向けてのヒマワリの鉢も準備してあって、花が咲き出したら今、ガードレールに置いて有る鉢と入れ替えになります。
ガードレールの上にヒマワリの鉢が並ぶの、なかなか綺麗で良いですよ!

さて、一通りの作業が終わった後は「反省会」です。
「反省会」とは言っても、自治会からの伝達事項や、次回以降に行いたい事の話や、お互いの近況等をざっくばらんに話します。
「景観整備の日」だけで無く何かと人が集まる際には、女性陣の方々が、ちょっとした昼食を準備してくださったりします。
この日も用意してくださってましたので、9月の「栃洞白山神社」の祭礼の話などをしながら美味しくいただきました。
さて来月8月は上にも書きました様に9月に「栃洞白山神社」の祭礼が有りますので、神社の清掃活動を重点的に行う予定です。
ここ栃洞は人数が少ない集落ですが、これからもお互いに協力し合って、より良い環境になる様に頑張って行きます!!